グローバル決済の変革――東京からナイジェリアまで、Web3は主流の枠組みにとらわれず何を生み出しているのか
本当の「金融包摂」は、実際に経験してこそその意味を実感できます。
先日日本を訪れた際、中国で日常的にQRコード決済を使っている自分に改めて気づかされました。日本では現金が依然主流で、カード決済は摩耗の原因となり、Suicaカードの設定やチャージも(特にAndroidユーザーには)手間がかかります。それでも、AlipayやVisa/Mastercardといった信頼できるバックアップがあるため、支払いが本当の障害になることはありませんでした。
しかし、アフリカや東南アジア、ラテンアメリカなど南半球の多くの国々に目を向けると、状況は全く異なります。こうした地域では、決済は単なる便利さではなく、生き抜くために不可欠なスキルとなっています。
銀行カードの利用率は非常に低く、多くの人が銀行口座自体を持っていません。小額の銀行間送金には高額な手数料と不安定な決済が伴い、多くの銀行は国際送金サービスを提供していません。利用できたとしても、その手数料は非常に高額です。
こうした場所では、決済はもはや水道や電気のような基本インフラではなく、「特権」となっています。
I. 世界は折り重なっている:東京からラゴスへ
東アジア(中国、日本)や欧米に住む人々にとって、決済サービスはしばしば「過剰に最適化」されているように感じられます。
WeChat Payのスムーズさ、Alipayの多機能性、日本のSuicaのタッチ決済は、資金移動は常に簡単であるべきだという錯覚を与えます。
ですが、世界は平坦ではありません。金融体験は「折り重なっており」、人によって大きく異なります。
まるでSF小説『折りたたみ北京』に登場する三つの物理的に隔てられた階級のように、グローバル金融も深く、ほとんど埋めがたいギャップで分断されています。「第一空間」の人々は二桁のDeFi利回りを追い、「第三空間」の人々は毎日賃金を無事に家に持ち帰ることに必死です。
注目すべきは、この文脈でしばしば見過ごされる逆説的な事実です。アフリカは「遅れている」と見なされがちですが、ナイジェリアのような新興市場では、人々はデジタル決済を望んでいるものの、インフラ面で阻まれているのです。
ナイジェリア中央銀行の最新データによると、インターネット送金は取引量の51.91%、POS取引は28.53%を占めます。これらのデジタル手段を合わせると全取引の80%超となり、ATM現金引き出しはわずか2.21%にとどまります。

このデータは、ナイジェリアの人々が特に銀行間送金などデジタル決済に強く依存していることを示しています。皮肉なことに、銀行支店など物理的な決済インフラは、デジタルバンキングソリューションよりもコストが高く、構築も困難です。
そのため、ナイジェリアでは「eウォレット」やその使い方を説明する必要がありません。人々は必然的に、ほとんど全ての送金をモバイルで行うことに慣れています。これは、Axie Infinityが東南アジアで現地のデジタル習慣を活かして普及した現象にも通じます。
唯一の課題は「接続性」です。ラゴスのフリーランサーや家族へ送金する出稼ぎ労働者にとって、平均15分以上の待ち時間や不利な為替レートは依然として大きなブラックボックスとなっています。
彼らはデジタル決済に頼っていますが、安定的で低コスト、かつグローバルに接続された決済インフラが不足しています。こうした背景の中、Web3はついに銀行システムに依存しない新たな道を示し始めました。
II. Web3決済:「農村から都市を包囲する」戦略
だからこそ、Web3やステーブルコインがアフリカやラテンアメリカなどの地域で「農村が都市を包囲する」アプローチで持つ革命的なインパクトと成長力は、主流の議論で過小評価されてきたと考えています。
最近、Xie Jiayin氏がベトナムでステーブルコイン決済を使った動画が話題となりました。正直、非常に衝撃的な内容でした。
ポイントは、決済が暗号資産ウォレット間の直接送金で完結し、U Cardなどの仲介が一切不要だったことです。

中国ではQRコード送金が日常ですが、AlipayやWeChatのような成熟したクローズド型決済ネットワークに依存しており、これは中国独自の環境と20年にわたるインターネット発展の成果であり、他国で再現するのは困難です。
動画で示されたモデルは全く異なります。ベトナムではBitget WalletがVietQRコードをスキャンします。フロントの体験はAlipayに似ていますが、バックエンドではSolanaの暗号資産送金を利用し、仲介プロトコルを介して法定通貨に即時変換、加盟店の口座に着金します。
最大の違いは「再現性」です。理論上、このベトナムモデルは現地即時決済システムがある国であれば導入可能です。
これは、スマートフォンやeウォレットが普及している一方、従来型金融インフラが未整備なアフリカやラテンアメリカで特に有効です。
ここで明らかになるのは、ユーザーがERC-20やガス代には関心がなく、「コードをスキャンするだけで簡単に支払いたい」という本質的なニーズであるという点です。
Web3決済におけるステーブルコインの進化を振り返ると、主に三つの段階がありました。
- 純粋なオンチェーントランスファー:ギーク向けのプロダクトで、NFTやDeFiでは有用だが、日常生活ではほぼ使われない;
- 「U Card」時代:暗号資産でVisa/Mastercardにチャージする形で、便利だがKYCやカード手数料・取引手数料の高さなど障壁が多く、結局は従来のカードネットワークに依存;
- 銀行へのダイレクト連携:オンチェーンアカウントやステーブルコイン資産を加盟店決済端末に直接接続し、カード発行会社やネットワークを介さずに取引する——これが現在最も注目される分野;
大手決済企業もすでにこの方向に動き出しています。
CircleはProgrammable WalletsやCCTP(クロスチェーンUSDC決済)をローンチし、StripeはステーブルコインAPIプロバイダーBridgeを11億ドルで買収しました。これらの動きはすべて第三段階を目指しています。
Bitget Walletのナイジェリア銀行送金新機能(Aeon Pay搭載)は、大手銀行やP2P以外の「第三の選択肢」を提供します。
- 分散型・KYC不要:従来の取引所で求められる煩雑な本人確認を回避し、Web3ウォレットの検閲耐性を維持;
- 超高速体験:P2Pマーケットの10〜15分の送金と比べ、ダイレクト連携により5〜10秒で送金完了;
- 低リスクチャネル:資金はコンプライアンスを満たした決済ゲートウェイ経由で銀行システムに直接入金され、見知らぬP2P業者を介さないため凍結リスクが大幅に低減;
これは、Web3ウォレットが資産管理ツールから中央銀行決済システム(ナイジェリアのNIBSS Instant Paymentなど)とのダイレクトAPI連携へと進化していることを意味します。
この流れを見れば、現在主流のU Cardもいずれ淘汰されるでしょう。伝統的金融機関は今後ますますWeb3決済ソリューションを組み込み、コンプライアンスを確保しつつ、ユーザーウォレット・加盟店決済・銀行口座や決済チャネル・決済システム間のダイレクトかつエンドツーエンドな連携を実現していくはずです。
III. 究極のPayFi:ウォレットが「見えない銀行」となるとき
ここで現実的な問いが生まれます。Web3は物理的な決済ネットワークを再発明する必要はなく、ウォレットが既存の決済ネットワークに「浸透」すべきです。
私が考えるPayFiの究極形は、Visa/MastercardやSWIFTに依存しない完全オンチェーン決済ネットワークです。
- 加盟店:ステーブルコインを直接受け取り、法定通貨への強制両替は不要;
- ユーザー:ノンカストディアルウォレットから直接送金し、自己管理で即時オンチェーン決済;
- バックエンド:コンプライアンスを満たすステーブルコイン発行者とオンチェーン決済ネットワークが支え、従来のカード組織による「通行料」を排除;
しかし、これは理想です。決済システムが根本から変わるまで、現実的かつ持続可能な道は、ステーブルコイン決済ゲートウェイを現地銀行に直接接続することです。
TradFiはコンプライアンス、口座構造、リスク管理に強みがあり、暗号資産はオープン性、グローバル流動性、トラストレス実行をもたらします。両者を組み合わせることで、「コンプライアンス」と「俊敏性」の最適なバランスが生まれます。
このトレンドはすでに現実となりつつあります。
前述の通り、Bitget Walletのナイジェリアでの導入例は「暗号資産」色を排除すれば、実質「グローバル流動性を備えたオフショアバンキングアプリ」となります。
ラゴスの一般ユーザーがBitget Walletを開くと、単なるオンチェーン資産管理ツールではなく、ドル(ステーブルコイン)を保管し、地元商店の銀行口座に即時送金できる「スーパーAlipay」として機能します。
これこそが新興市場向けPayFiキラーアプリのプロトタイプとなり得ます。
Web3ウォレットが世界中のリアルタイム決済システム(ナイジェリアのNIBSS、ブラジルのPIX、インドのUPIなど)にコンプライアンスを維持したままシームレスにアクセスできるようになれば、このモデルは従来のSWIFTシステムの高コスト・非効率をついに回避できるでしょう。
近い将来、Bitget WalletのようなプロダクトがAirwallexやWiseなどのクロスボーダー決済ソリューションをコスト・ユーザー体験の両面で凌駕する可能性も十分にあります。
まとめ
決済はステーブルコインの出発点です。「グローバル決済」は、その進化がグローバル金融インフラの中核となることを意味します。
ベトナムのQR決済統合やナイジェリアのオフチェーン銀行送金は、ステーブルコインの最大の価値が銀行を置き換えることではなく、銀行がカバーできないギャップを埋めることにあると示しています。
今後も、より多くのウォレットやWeb3プロジェクトが、こうした複雑な現地環境で実験と深化を続けていくことを期待します。
そうして初めて、「グローバル決済」は単なるバズワードではなく、日常の現実となるでしょう。
免責事項:
- 本記事は[TechFlow]より転載したものであり、著作権は原著者[Web3 Farmer Frank]に帰属します。転載に関してご懸念がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡ください。関係手続きに従い対応いたします。
- 免責事項:本記事に記載された見解や意見は著者個人のものであり、投資助言を構成するものではありません。
- 本記事の他言語版はGate Learnチームによって翻訳されています。Gateの明示的な参照なしに、翻訳記事の無断転載・配布・盗用を禁じます。
関連記事
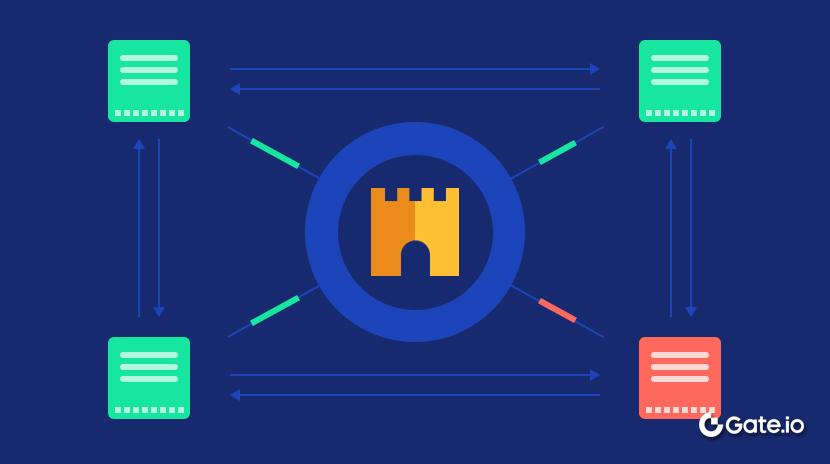

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

分散型台帳技術(DLT)とは何ですか?
