EigenLayerによるリステーキングの潜在力を検証
元タイトル『重新理解 EigenLayer 再質押潜力:突破信任界限』より転載
TL;DR
Ethereumのようなブロックチェーンは、相互に信頼しなくても協働できる仕組みを提供しています。しかし、その協働はオンチェーンで検証可能な情報に限定されます。EigenLayerは「真実とは何か」の定義領域を拡張し、この信頼の幅を広げます。
EigenLayerでETHを再ステーキングすることで、複数のサービス(AVS)の同時保護が実現し、資本効率が高まり、より連携した効率的なエコシステムが生まれます。
EigenLayerは二重トークンモデルによって、間主観性や社会的真実の課題に対応します。結果に異議が出るたび、ステークトークンが分岐します。
AVSは新規プロジェクトの参入障壁を下げますが、プロジェクト側はEIGENおよびETHステーカーへの収益分配、もしくはトークンインフレによる流動性・セキュリティ補償が必要です。
2024年の暗号資産市場では、EigenLayerがもたらした新たなプリミティブの影響で再ステーキングとLiquid Re-Staking Token(LRT)が注目を集めています。以下の図は、LRTやリキッドステーキングデリバティブ(LSD)のストーリーの変化を示します。

出典:Kaito
EigenLayerプロジェクトの本質を一言で表すなら、「分散型信頼の境界を広げること」です。再ステーキングの仕組みはDeFi資本の効率性を高め、EIGENトークンはガバナンス領域を広げます。
私はこの分野の進展を常に追っており、再ステーキングがバリデータやエコシステム全体に与える影響について考察を深めてきました。仕組みの解説だけでなく、「間主観性」というテーマも掘り下げます。EigenLayerのホワイトペーパー初公開時、この概念は非常に学術的に感じましたが、ブロックチェーンのガバナンスや分散型信頼を考える上で本質的なトピックです。詳しく見ていきます。
再ステーキングとは何か
再ステーキングの詳細に入る前に、私が過去に取り上げたレイヤードビットコインの記事を振り返ります。暗号資産の分野は常に限界を押し広げており、レイヤードブロックチェーンは画期的な新機能を生み出しています。再ステーキングは、バリデータのダイナミクスや資本効率の認識を変える新たなレイヤーとして登場しました。
ブロックチェーンは「信頼のマシン」です。参加者は価値ある資産を担保として預け、信頼の必要性を置き換えます。ルールを守れば報酬があり、違反すれば担保が没収されます。
EigenLayerについては、Jordan McKinney氏の動画で理解が深まりました。この動画は、技術詳細に踏み込めない方にもEigenLayerの全体像を分かりやすく解説しています。要点は次の通りです:
EigenLayerは、Ethereumを守るETHを利用してActive Validation Services(AVS)も同時に守ることを可能にします。追加報酬を得られるだけでなく、バリデータに新たな責任と機会をもたらします。現在、流通ETHの約28%(3,400万ETH)がバリデータによってステークされ、EigenLayerには約470万ETHが再ステーキングでロックされています。
ビットコインからEigenLayerまで
EigenLayerの利点を深く理解するには、ブロックチェーン技術の進化を振り返る必要があります。ビットコインはProof of Work(PoW)を導入し、マイナーが電力やハードウェアでネットワークを守る構造を実現しました。これは画期的でしたが、機能は価値保存や決済にほぼ限定されており、これが高いセキュリティと分散性の基盤となっています。
一方で、ビットコインは設計が硬直的です。マイナーはネットワーク保護以外にハードウェアを使えず、資本効率が制限されます。資本効率とは、投資した資本から最大の成果や価値を得ることです。資本効率の制限は欠点ではなく、ネットワーク利益の優先を保証する設計です。この流れが次の技術的躍進につながりました。
Ethereumは、汎用計算を導入し、アプリケーションを構築できる基盤を提供しました。バリデータはETHをステークし、Ethereumとその上で稼働する多様なアプリケーションの双方を守ります。これにより、同じ資本でブロックチェーンとアプリエコシステムの発展を支えられるようになりました。ただし、Ethereumはスケーラビリティの課題を抱えています。
そこで、Ethereumの処理能力を大幅に向上させるLayer 2(Rollupなど)が登場。スループットは12~15TPSから、Rollup利用で約200TPSへと向上しました。しかし、Rollupシーケンサーは中央集権化リスクがあり、通常はRollup運営者が管理し、トランザクションの順序を決めます。
このリスクを減らす方法の1つが、複数のシーケンサーに資本ステークを義務付け、ブロック生成と手数料取得の権利を与えることです。ただし、シーケンサーのステーク資本はEthereum本体のステークETHとは分離され、資本効率が下がります。

再ステーキング:資本効率の向上
従来のPoSでは、バリデータはネットワーク保護のため資産をステークします。もし同じETHで追加サービスも守れるなら、資本効率はどうなるでしょうか?これが再ステーキングの発想です。バリデータはEthereumを守るだけでなく、EigenLayerで他のサービスも守るためにETHを再ステークできます。
再ステーキングは既存リソースの活用を最大化する自然な進化です。責任範囲を拡大すれば追加報酬も得られ、ネットワーク全体のセキュリティと効率も高まります。
EigenLayerは、Ethereumのセキュリティを担保するETHをそのままAVSにも利用できる仕組みです。具体的には、バリデータはETHステーク時、出金アドレスとしてEOAではなくEigenPodスマートコントラクトを指定します。EigenPodがバリデータとAVSの仲介役となり、定義済みの基準でバリデータの実績を評価し、出金時にETHのスラッシュ可否を判断します。
再ステーキングは単なる報酬増加策ではなく、ブロックチェーンエコシステムにおける資本の概念そのものを変えます。従来は資本をステークしたらネットワーク保護にしか使えませんでしたが、再ステーキングは同じ資本で複数の役割を実現し、その活用を最大化します。
ただし、再ステーキングにはリスクも伴います。バリデータはEthereumのルールだけでなく、AVSの要件にも注意が必要です。責任が増す分、どこかで失敗すればスラッシュや損失リスクも高まります。
影響の定量化
事業インパクトは数値で示されることが多いです。再ステーキングの基本を踏まえ、その効果をエコシステム全体で考えます。AVSはETHバリデータに基本ステーキング報酬を超える追加収益をもたらします。
現在、ETH流通量の約27%がステークされています。ETHステーク量の増大により、基本利回り(ベースイールド)は低下傾向です。これは設計上、利回りの増加速度が資本の増加より遅いからです。バリデータは収益維持のため新たなインカム源が必要となり、ここで再ステーキングが生きてきます。
下のチャートは、AVSがバリデータにもたらす追加報酬の感度を示します。必要な指標はETH時価総額、ステーク率、AVS追加利回りの3つです。例えば時価総額6,000億ドル、50%ステーク、AVS1%追加利回りなら、年間30億ドルの報酬増です。こうした定量的向上は、再ステーキングの価値を明確に示し、EthereumのようなPoSネットワークの将来の主要イノベーションとなります。

再ステーキングによる追加報酬は、単なる収益増加以上の意味を持ちます。ETHのステーク増で基本利回りが低下する中、利益維持のため再ステーキングが最適解となり得ます。EigenLayerはバリデータに多様な収益機会を提供し、ネットワークのセキュリティ維持と参加意欲の向上を実現します。
一方、再ステーキング導入でステーキングプロセスも複雑化します。バリデータはAVSごとのパフォーマンスやセキュリティ、各サービスに関するリスクを考慮しながら、リスクとリターンを見極めた戦略が必要となります。
現状、AVSにはスラッシュ機能がありません。そのため、バリデータはコストなく新AVSに参加し報酬を得られます。今後スラッシュが実装されれば、参加できるAVS数が減り、新規報酬チャンスも減少する見込みです。
間主観性:チェーン上で証明できない真実
ミームコインや投機的取引が注目される中で、トークン本来の役割を見失いがちです。EthereumのETHは単なるガストークンではなく、ネットワークのPoSコンセンサスを担い、ブロックチェーン運用の安全性を支える暗号経済的セキュリティの核です。ETHなくしてEthereumは機能しません。
トークン設計段階で、機能は事前に決める必要があります。これらの制約がトークンの実用性を左右し、後で変更はできても、ブロックチェーンの不変性や予測性という原則の下で社会的合意形成は困難です。

ここで視点を変えます。以前の記事「Humpy vs Compound DAO」でも触れた通り、ブロックチェーンは技術だけでなく、人やコミュニティが関わる分野です。ここで「間主観性」という概念が重要になります。一見哲学的ですが、実はブロックチェーンガバナンスに深く関わっています。

間主観性とは、オンチェーンで証明できなくとも、合理的な参加者なら社会的真実として認める事象です。たとえば「ETHが10ドル」というデータがあっても、異議が出れば大多数は誤りと判断します。EigenLayerのEIGENトークンは、こうした間主観的課題の解決を目指しています。
EigenLayerのアプローチは、ブロックチェーンの客観データだけですべての意思決定ができるわけではないと認めている点が特徴です。データ可用性サービスを例にとると、ネットワークノードはデータの保存とリクエスト時の取得を証明する必要があります。しかし、ノードが結託して存在証明を作っても、実際にはデータがダウンロードできないこともあります。こうした場合、「多数派の専制」にユーザーが異議を唱える手段が必要です。
これは、ネットワークの多数決判断がエコシステム全体の最善とならない場合や、少数・個人を不当に扱う場合に対応するものです。EigenLayerは、こうしたシステム課題にユーザーが異議申し立てできる仕組みを提供します。
好き勝手に異議を申し立てられるわけではありません。チャレンジにはコストがかかり、一定量のトークンをバーンして開始します。
現実世界では、オンチェーンで証明できない真実も多いものです。ブロックチェーンは厳密な二択判断には強い一方、証明困難な領域は苦手です。EigenLayerはガバナンスに間主観性を導入し、このギャップを埋めます。Ethereumのようなブロックチェーンは信頼なき協働を可能にしますが、オンチェーンで証明できる範囲に限られます。EigenLayerは「真実」の定義領域を広げ、その信頼の幅を拡張します。
たとえば、バリデータの悪意ある行為が疑われた場合、証拠が曖昧で意図が問われることもあります。従来のブロックチェーンは客観データ重視のため、こうした紛争解決は困難です。しかしEigenLayerの間主観的アプローチでは、コミュニティが事実や判断を総合し、意思決定できます。
仕組みはどうなっているか
通常、オンチェーンで紛争が生じるとブロックチェーン自体がフォークします。たとえばEthereumは2016年のDAOハック後にフォークしました。「コードが法」ならフォークは起こらなかったはずですが、社会的合意がネットワークのためにフォークを選択しました。
EigenLayerはEthereum上の仕組みで、ベースレイヤーブロックチェーンやL2のフォークはありません。紛争が起きるとEIGENトークンがフォークします。EIGENはEthereum上のコントラクトで、フォーク時は新たなコントラクトがデプロイされ、トークン所有権が移ります。有罪や悪意ある当事者には、フォークトークンの減額や喪失などのペナルティが課されます。
デュアルトークンモデル
従来のステーキングやガバナンスは、単一トークンでステーキングやDeFi利用など全ての機能を担ってきました。しかし、これではオンチェーンだけで解決できない複雑な紛争に対応しきれません。EigenLayerは、EIGENとbEIGENという2つの関連トークンで、柔軟性とセキュリティを高める新モデルを導入しています。
- EIGEN:非ステーキング用途のトークンで、DeFiでの保有や取引、アプリ利用などに使えます。ステーキングやガバナンス紛争のリスクは直接負いません。
- bEIGEN:EigenLayerのステーキング専用トークンです。ステーキング参加時にEIGENをbEIGENにラップし、以後はスラッシュやフォークなどのリスクを負います。

このように機能を分離することで、EigenLayerは柔軟で堅牢な仕組みを実現。ステーキングに関心のないEIGEN保有者は、ガバナンスや紛争解決を気にせずエコシステムで利用でき、bEIGENは責任とリスクを明確化したステーキング用トークンとして機能します。
デュアルトークンモデルの仕組み
データ可用性問題や誤ったオラクル情報など、オンチェーンで簡単に解決できない問題が生じた際、bEIGENはフォークし、元の状態とコミュニティ解決後の2つのバージョンが生まれます。
この分離により、紛争の結果は直接ステーキングに関与するbEIGEN保有者のみに影響し、EIGEN保有者はEIGENをbEIGENに変換しない限り影響を受けません。
デュアルトークンモデルにより、EigenLayerは複雑な間主観的課題にもエコシステム全体への影響を最小限に抑えながら対応できます。ステーキング関連と他の用途を明確に分離し、分散型ガバナンスや紛争解決に強い柔軟なプラットフォームを実現しています。
EigenLayerの実例
私は「フォーク」というアイデアに強く惹かれてきました。暗号資産の世界だけでなく、人生の選択や分岐の比喩でもあります。ブロックチェーンでのフォークは、ネットワークの方向性を左右する重要な決断です。EigenLayerのフォークメカニズムは、コミュニティ合意による紛争解決の好例です。
具体例でその仕組みを見てみましょう。
最近、PolymarketではRobert F. Kennedy Jr.大統領選キャンペーンの予測市場決着を巡り論争がありました。Kennedy氏が撤退を表明した直後、選挙権申請や活動継続発言があり、参加者間で議論が過熱しました。2度のチャレンジ後も市場結果は「YES」とされ、UMAオラクルの決定にも納得できない声が上がりました。この問題は、UMAが「関与」していなかったことも一因です。
EigenLayerの間主観的フォークなら、こうした論争もより動的に解決できる可能性があります。関係者が市場フォークを発動し、「撤退」と「継続」の2つの結果に分岐、コミュニティ投票で支持された解釈が主流となります。これにより、参加者の利益が結果の正確性と公平性により強く結びつきます。
EigenLayerの間主観的フォークを用いれば、予測市場でも複雑な状況に柔軟に対応でき、より広いコミュニティ合意を反映した決着が実現し、信頼性と健全性が保たれます。
EigenLayerでチャレンジャーが高コストを負担する仕組みを思い出してください。新しいフォークトークンの発行には、既存のbEIGENを一定量バーンする必要があります。コミュニティが正当と認めれば、新フォークトークンの価値を獲得し、報酬を得られる可能性があります。
チャレンジ内容に応じてbEIGEN保有者は支持するフォークを償還できます。複数のフォークが共存する場合でも、その価値は市場で決まります。理想的にはEIGENの価値=bEIGENとそのフォークの合計価値となります。あるフォークの償還が他より著しく多ければ、コミュニティの意思決定が明確になります。
これらの例は理論上だけでなく、実際にEigenLayerネットワーク内で発生しうる現実のシナリオです。柔軟なガバナンスシステムの重要性を示しています。
エコシステムのニーズと経済的課題のバランス
EigenLayerは分散型信頼拡張の新モデルを提供する一方、AVSにとって新たな課題も生じます。独立運用で価値最大化を目指すAVSもあれば、エコシステムの基盤サービスとして設計され、他のサービスやプロダクトとの相互需要で恩恵を受けるAVSもあります。
こうしたAVSにとって、EigenLayerエコシステムへの参加はユーティリティや需要喚起につながり、初期導入課題の克服にも役立ちます。ETH/EIGENステーカーとの収益分配は、エコシステム需要やセキュリティ共有の合理的な対価です。この関係性が相互接続型サービスネットワークの形成につながる可能性はありますが、長期的な持続性は未知数です。
一方、独立系AVSには別の課題もあります。独自チェーンを目指す視点では、ETH/EIGENステーカーとの収益分配コストと、別チェーンでのセキュリティや流動性確保コストを比較する必要があります。EigenLayerは大規模なセキュリティプールとユーザー基盤を提供しますが、サービス成長に伴い長期的な戦略の見直しも求められます。
複雑な状況への戦略的対応
要するに、EIGEN・bEIGEN・フォークメカニズムの組み合わせが、ブロックチェーンガバナンスの新領域を切り開きます。コミュニティによる間主観的紛争解決で、分散型システムのセキュリティと適応力が高まり、より強靭で柔軟なエコシステムが期待できます。
プロジェクトが進化する中、新たな課題も生まれます。EigenLayerは独立導入と比べて競争力ある収益共有環境を維持できるか。このモデルは本当にイノベーションを促進できるのか、それとも新たな依存や中央集権を生むのか。
確かに複雑ですが、それが本質です。既存のDeFiプロトコルとの統合は容易ではなく、多様な課題があります。しかし、ブロックチェーンは困難であるべきであり、私たちに思考と探求を促します。
結局のところ、EigenLayerは再ステーキングや追加報酬だけではなく、分散型信頼の境界拡張を目指すものです。オフチェーンの事象にも対応でき、コミュニティ合意が最終的な真実の裁定者となる新たなシステムを志向しています。
免責事項:
- 本記事は[ForesightNews]より転載しました。元タイトル『重新理解 EigenLayer 再質押潜力:突破信任界限』より転載。著作権は原著者[Saurabh Deshpande]に帰属します。転載にご異議のある場合は、Gate Learnチームまでご連絡ください。関連手続きに則り速やかに対応いたします。
- 免責事項:本記事の見解・意見はすべて著者個人のものであり、投資助言を意図したものではありません。
- 他言語への翻訳はGate Learnチームが担当しています。特記なき限り、翻訳記事の無断複製・配布・盗用を禁じます。
関連記事

ETHを賭ける方法は?
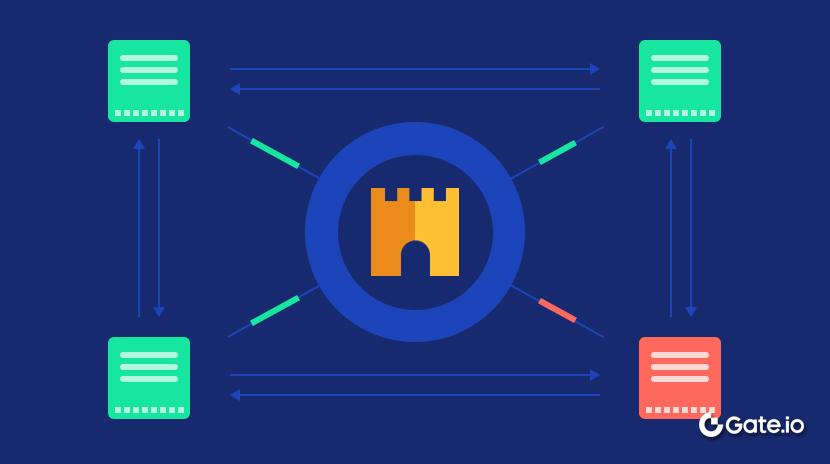

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?
