DOGEは現在も解散せず、どのような活動を続けているのか?
過去2週間、暗号資産コミュニティでは、Bitcoinの価格下落とそれを引き起こすマクロ経済要因――CPIデータ、政府の刺激策、AIバブル、流動性、米国債利回り、ETF流出、米国最高裁による関税判決など――についての議論がほぼ独占的に行われてきました。
しかし、私はEthereumのチャートとこの数年の軌跡に改めて注目したいと思います。
Ethereumの価格変動は非常に大きく、外部の人からはETHを大量に保有する投資家の生活が平穏そのものに見えるかもしれません。
多くのCrypto Twitter(CT)ユーザーも、このLayer-1ブロックチェーンに対して同様の印象を持っています。Ethereumは「世界のコンピュータ」「ネットワークインフラの未来」「ウェブの金融レイヤー」など、さまざまな呼称で語られています。
今回は、Ethereumのマーケティング戦略の失敗が、市場による過小評価や本来の可能性の誤認を招いた経緯を振り返ります。
この点を説明するため、Equilibrium LabsのパートナーであるMika Honkasalo氏とSaurabh Deshpande氏へのインタビュー内容を引用します。

主なポイントは以下の通りです。
Ethereumの「アイデンティティ・クライシス」:誤解された価値
このサイクルを通じて、ETHに関する議論はしばしば感情的に展開されてきました。Bitcoinが最高値を更新するたび、暗号資産コミュニティではEthereumのパフォーマンスに対する揶揄が飛び交い、まるで2番目に大きなネットワークがBitcoinの動きをすべて追随すべき義務があるかのような空気が生まれます。
Ethereumの設計には「マネタリープレミアム」を保証する仕組みはありません。
それでも、市場がEthereumに過剰な期待を寄せてしまう理由は理解できます。
Bitcoinのミッションは明快で一貫しています。有限供給によって価値を高める「デジタルゴールド」として、ドル建てで価値保存手段となることです。
一方、Ethereumの価値は複数方向に引き裂かれています。透明性、セキュリティ、不変性、スマートコントラクトによるプログラマビリティなど、根本原則のバランスを取っています。
こうした状況下で、Ethereum Foundationが本来の目標やビジョンを十分に発信してこなかったことで、多くの人がEthereumをBitcoinのような通貨と誤認するようになりました。
このことが2つの異なる見方を生み、一部ではマーケティングの失敗による「アイデンティティ・クライシス」とも呼ばれています。
ブランド差別化:Ethereum vs. Solana
Mika氏はSolanaのブランド戦略を引き合いに出しています。
Solanaに関するミームやジョークはあるものの、このプロジェクトは2年間にわたり「分散型Nasdaqをほぼ光速で構築する」というメッセージを徹底して発信してきました。

この捉え方に賛同しない人もいるかもしれませんが、Solanaのメッセージは一貫しています。何でもできると主張したり、通貨の代替を目指したりすることはありませんでした。
一方Ethereumは、Web3のインフラ、ultrasound money、デジタルオイルなど、ストーリーが断片化しています。
それぞれの呼称には一定の根拠がありますが、明確な主目的や統一されたビジョンには結びついていません。
これらのアイデア自体に問題はありませんが、焦点の欠如はビジネス上の弱点となり得ます。市場はETHをマネタリーナラティブでひとくくりにしがちです。ネットワークはWeb3の分散型金融プロトコルの基盤へと進化しているにもかかわらずです。
Mika氏は、暗号資産プロジェクトをキャッシュフロー創出装置として捉えるべきだと提案していますが、ここにパラドックスがあります。Ethereumは決済レイヤーとしての役割を強める一方、ほとんどの取引や手数料、ユーザー活動は、よりコスト効率の高いLayer-2ネットワークで行われるようになっています。
その結果、市場がETHの価値を手数料バーンメカニズムに結び付けようとすると、効率性の向上が両刃の剣となります。L2への活動移行が進むほど、メインネットのデフレ効果は弱まるのです。
Ethereumの独自の優位性:デジタル資産トレジャリー(DATs)のパフォーマンス
別の観点も考慮すべきです。Ethereumやそのコミュニティは、目標や意図をマーケティングする必要はないと主張する人もいます。
Ethereumの独自性は特定領域で特に際立っています。
デジタル資産トレジャリー(DATs)の運用方法を考えてみましょう。Ethereumを多く組み入れたDATsは、Bitcoin中心のDATsよりも高いパフォーマンスを示しています。ETHをステーキングすることで利回りが得られる一方、Bitcoinにはその仕組みがありません。
この違いにより、組織が市場サイクルを乗り切る方法が変わります。
Bitcoinトレジャリーは市場の変動に左右されます。価格が上昇すればバランスシートは力強く見えますが、流動性が枯渇した場合(現在のように)、根本的な脆弱性が表面化します。
最悪の場合、DATsがほぼBitcoinのみを保有し、運用収益がほとんどない場合、毎月の費用を新株発行で賄うことが多いです。利回りも内部エンジンもなく、資産をポートフォリオ以上に活用する術がありません。
Ethereum DATsは単なるETH保有者ではありません。ステーキングやリステーキングによるネイティブ利回りの獲得が可能です。ETH建てトレジャリーはエコシステム経済に積極的に参加できます。このように、ステーキングされたETHは投資家を市場サイクルから守る役割を果たします。
こうした側面はEthereumのマーケティングではほとんど語られません。コミュニティが自己宣伝を避ける傾向もその一因です。
しかし、ETHのトレジャリー資本観点からの実際のパフォーマンスを詳細に分析すると、その資産本来の性質が明らかになります。実利用、オンチェーン活動、エコシステムの相互運用性によって価値が複利的に増加するのです。
Mika氏はEthereumの未来を「10億人が本当に必要とするプロダクトを構築できるかどうか」に結び付けています。また、Coinbaseによる流通のおかげでBaseが最も成功したL2となったことにも言及しています。Ethereumの将来も同じ核心要素にかかっているかもしれません。
Ethereumがマーケティングに長けているかどうかは重要ではありません。DeFiプロジェクトの基盤であり続け、各プロジェクトが主流への普及を牽引できれば十分です。多様なアプリケーションや消費者向けプロダクト、L2が決済レイヤーとしてEthereumを選び続ける限り、ネットワークはブロックスペースの需要と安定した手数料収入の恩恵を受け続けます。
Ethereumの成長パスはAmazon Web Services(AWS)に似ています。Amazon社内でゆっくり成長した低利益率の実験から始まり、最終的には企業の最重要事業となりました。
声明:
- 本記事はblocktempoから転載したものであり、著作権は原著者Bitpushに帰属します。転載についてご懸念がある場合はGate Learnチームまでご連絡ください。弊社手続きに従い速やかに対応いたします。
- 免責事項:本記事の見解・意見は著者個人のものであり、投資助言ではありません。
- 本記事の他言語版はGate Learnチームが翻訳しています。Gateの記載がない限り、翻訳記事の複製・配布・盗用はできません。
関連記事
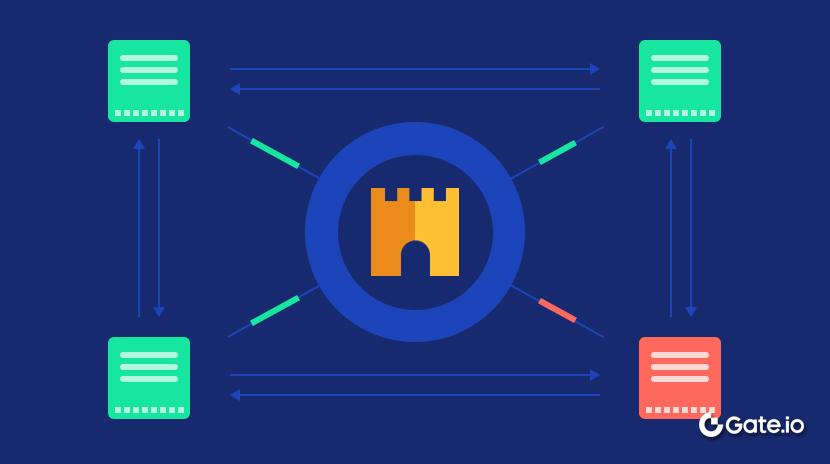

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

分散型台帳技術(DLT)とは何ですか?
